レポート
脱炭素化技術のテクノロジーアセスメント フロントランナーへのインタビュー PART3
脱炭素化技術のテクノロジーアセスメントプロジェクトでは、2021年9月〜12月に、持続可能な未来社会における新たな常識や価値観を構想し、その実現に向けて各分野で活動されるフロントランナー(FR)の方々19人に、個別にインタビューを行いました。
プロジェクト側から、本プロジェクトやテクノロジーアセスメントの趣旨、評価枠組の素案について説明するとともに、各FRの活動領域や専門分野の見地から、脱炭素化技術のELSIを検討・評価する上で考慮すべき観点や事柄について、それぞれ約1時間お話を聞かせていただきました。
インタビューを6回に分けてご紹介します。
———
PART3
- 地域住民の「思い」を枠組の中で評価できるか………………………………倉田哲郎さん
- QOLや公平性の観点からマイノリティの問題を考える ……………………山田小百合さん
- 自然や文化などの内在的価値の重要性……………………………………………辻井隆行さん
———
地域住民の「思い」を枠組の中で評価できるか
元自治体首長、総務官僚
倉田 哲郎さん
 ―評価枠組案をどのようにご覧になりましたか。
―評価枠組案をどのようにご覧になりましたか。
倉田:比較的大がかりな電源や発電所の話は、評価枠組のマトリックスに当てはまる印象を受けます。一方で小・中規模の電源、例えば太陽光パネルを設置する上での地域における課題は、この枠組で評価できるのでしょうか。ここ10年ほど小規模の太陽光パネルを設置する動きがありますが、それに伴う光の害(光害)は、面的に広がると、当たり所が悪い家ではかなり眩しくなるそうです。
箕面市では、一定規模以上の太陽光パネルを置く時には、事前に届け出をしてもらい周辺の住宅への光害のシミュレーションを行っています。また、地域の景観を阻害してしまう恐れもあり、条例で規制をかけました。そのような住民の感情をどのように受け止めるのか、この評価枠組の中では十分に捉えきれない可能性がある、という印象を受けました。
原発のような大規模かつ集中的に電力を作る技術に関しては、自治体に交付金を渡してお金で解決するような国の枠組があります。ただ、脱炭素系の技術を見ていると、小規模な発電、例えば小水力なども含めて、地域に分散して電源を作る話がどうしても出てきます。民間がビジネスベースで事業をできるようにしないと、技術が普及しないという側面がありますが、事業者主導で推進する場合、今度はそこでコンフリクトが起こる可能性があります。そのコンフリクトとは一体何なのか。それが一つのポイントだと思います。
―再生可能エネルギー開発の地域生活への影響は、評価枠組の中でその影響を細分化して検討することも可能です。ただ、住民の感情はもっと曖昧なものであり、複合的に理解すべきものではないかというお話かと思います。箕面市で太陽光に規制をかける判断をした背景には住民の思いがあったと思いますが、一番大きな要因は何だったのでしょうか。
倉田:直接のきっかけは、箕面市に隣接する豊能町でメガソーラーの開発に対する住民の反対運動が起こったことです。箕面市でも同じような状況が起こり得ると考えて、事前に手を打ちました。ただ、この問題はなかなか定量化が難しく、苦慮するところです。箕面市の場合は、同市の北側に位置する山並みが、まちにとっても非常に重要な景観要素であり、建築物の規制等を通じて、その視線を遮らない方向性を、長年かけて確立してきました。では、なぜ山麓部が箕面市にとって大事なのかと言われたら、多くの人が「いいところだね」と言って住んでいる。そのような漠然とした社会的コンセンサスがあるとしか言いようがありません。だからこそ、このような評価枠組の中でも気をつけておくべき1つのファクターなのかもしれません。複数の価値が併存している場合、それらをうまく比較できるようにしておかないと、住民と自治体とのあいだのコンセンサスは取りづらいと思います。
評価枠組の中では、「生活の質(QOL)・健康及びwell-being」や「文化・伝統・自然などの内在的価値」の中に大枠では位置づけられると思います。この評価枠組は、科学技術の導入について、事前に評価をして、その先の事を考えるための枠組だと理解しています。ただ、太陽光パネルの事例は問題が発生した後の出来事であり、必ずしも事前に予測できるわけではありません。もしかしたら、この現状の枠の中がもう少し細分化されて、より具体的な類型が示されれば、未だ起こっていない事象に対してのヒントになるかもしれません。
―「将来」や「未来」について、どれくらいのタイムスパンで考えることが多いですか。
倉田:市長というマネジメントをする立場のときは、おおよそ10年と30年の二本立てで考えていました。
例えば、道路行政については、まちそのものをマクロで眺めて、この渋滞は将来的に解消されるのか。その場合、いつ頃になるのか。そのためにはどのような手順で道を広げていけば解消されるのか。そう考えると、現在そこに住んでいる人に立ち退いてもらい、道を広げるという話になります。そのような物事は10年で終わる話ではなく、30年ぐらいのスパンの話になります。私の子どもが大人になった頃をイメージして、今できるのはここまでだけれど、そのためのルールを作っておいて、このルールが適用されることで、30年後の未来が姿を現すのではないか。そのような時間軸が1つあります。
一方で、比較的短期間で物事を変えたり、直したりできることに関しては、おおよそ10年後ぐらいには全市域で問題は解決しているのではないか。そのような感覚で取り組んでいました。
―その二つのタイムスパンの中で、日本社会全体として変わっていくべき点、逆に変わらずに残していくべき点は何だと思いますか。
倉田:自治体や国での仕事の経験を踏まえると、意思決定をする仕組みが、比較的目先の事になり過ぎている印象があります。国民や住民の関心も、比較的許容性が狭くなっていて、負のスパイラルに陥っている印象を受けています。例えば新型コロナウイルスの対応に関して、経済活動との両立を当然していかなくてはいけません。ただ、どちらかというと、ウイルスへの恐れが先行している印象です。例えば、道路行政一つとってみても、道路拡張の際の立ち退きに関して、世論はどちらかと言えば「立ち退く人が可哀想」といった話に傾きがちです。そうなると、当初掲げた道路計画を取り下げざるを得なくなり、行政も腰砕けになってしまいます。もちろん説明する行政の側の問題もありますし、受け手側の問題も両方あるように思います。
―そうした問題に比べると、気候変動問題は、自分たちのまちのことですらないと思われてしまうのでしょうか。
倉田:すごく遠い世界の話のような印象です。特にエネルギーの話にしてみても、発電所などが立地する場所の住民にとっては身近に感じますが、多くの国民にとってはどこか遠くの話という印象しかありません。
―自分たち自身の問題と捉えてもらうためには、国民一人ひとりからボトムアップしていく方向性と、30年先の世界の話であればトップダウンの方向性も考えられます。
倉田:多くの住民が将来の価値を正確に理解することに対して、いかに説明を尽くしたとしても、そこには限界があると思っています。気候変動に関しても、そのための技術開発や導入に関しては、多くの人たちの理解を得る必要がありますが、その理解を得るためのコミュニケーションとして、全ての真実をありのままに伝えることが、コミュニケーションをとる上で良いかと言われると、疑問を感じる部分もあります。コミュニケーションをうまく進めようとすれば、分かりやすくデフォルメをしたり、比較的多くの方々の関心に刺さる部分を強調して伝えたりすることがあると思います。当然、そこで間違った技術が選択されると困るので、そこはプロの世界でしっかりとやらなければいけないと思います。ただ、その技術を実際に社会で共有させていく段階では、伝え方にもある程度のデフォルメが必要ではないでしょうか。
(2021年9月21日、オンラインでインタビュー)
くらた てつろう
株式会社アルファ建築設計事務所上席部長、前・箕面市長
1974年生まれ。郵政省と総務省の職員、大阪府箕面市への出向などを経て、2008年同市長に就任。3期12年務める。徹底した行財政改革を進める一方、多彩な政策とスピード感のある行政運営を展開。市長時代に人の流れを変える建築の機能に注目し、二級建築士の資格を取得。20年8月より現職。*所属・役職は当時
QOLや公平性の観点からマイノリティの問題を考える
NPO代表(インクルーシブデザイン)
山田 小百合さん
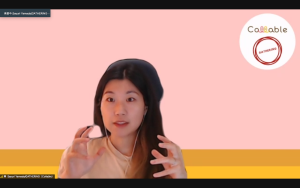 ―評価枠組案をどのようにご覧になりましたか。
―評価枠組案をどのようにご覧になりましたか。
山田:私たちの仕事と最も関連があるのは「生活の質(QOL)・健康well-being」と「公平性・権利」の部分です。私はインクルーシブデザインの分野と、そこから派生して最近は障害のある学生の学習支援に取り組んでいます。背景には貧困問題があり、経済的な要因だけでなく、愛着や関係性の貧困の問題もある。そのため、QOLやwell-beingは障害のある人のキャリアを考える上で大事になってきます。自分たちが自立的に生きていけるのか、働いて安定的にお金がもらえるのか。そういった文脈であれば、この分野は、気候変動に関わらず様々な領域について語りやすい切り口だと思います。
障害の分野では、どのようなコミュニティやネットワークから情報を得るのか、マイノリティの属性によってばらつきがあり、情報を入手するチャンネルも煩雑化します。評価枠組で言えば「公平性・権利」の観点から見た「社会を通じた影響」に関わってくる話です。気候変動に関して、障害のある人の中でも、情報に敏感で問題に取り組みたいと思う人も出てくるかもしれませんが、多くの人は、生活に余裕がなくて実際には難しいという方向に落ち着くような気がします。
―例えば自動車はEV(電気自動車)にしか乗れないという方向に世の中が変わると、生活に自動車が必要な障害のある人は、その影響を一気に受けることになります。その点はどう考えればよいでしょうか。
山田:社会的に影響力がある出来事により自分の周囲が明らかに変わっていくと、マイノリティの中でも感度の高い人が、インフルエンサーのようなかたちで、自分たちと似た境遇の人に対して、率先して情報を発信することはよくあります。また、マイノリティの人たちの中にもそれぞれのコミュニティがあります。
―マイノリティの中でインフルエンサーになる人は、話題横断的に社会問題をキャッチして発信するのか、あるいは特定の話題ごとに情報発信するのでしょうか。
山田:その二つの軸で言えば、話題横断的だと思います。ただ、結局は自らの障害に起因することが発信の軸になるので、自らのキャラクター性を踏まえての発信になると思います。
―今年2021年にはパラリンピックが開催されました。障害者を取り巻く社会の状況について、この2、3年で変わってきた印象はありますか。
山田:ものすごく変わってきたと思います。企業がSDGsを意識してダイバーシティ、インクルージョンをとりあえず取って付けてでも喧伝するようになったのは、大きな変化だと思います。それはパラリンピックが牽引してくれた部分も大きいと思います。
私たちの取り組みも説明しやすくなりました。以前は「ダイバーシティ」や「インクルージョン」といった言葉を発しても、互いの認識が異なっていることがよくありましたが、最近は前提が共有された状態で議論できる機会が増えました。気候変動にも関連するSDGsのコンテンツは、周りでも幅広く扱われるようになっているので、それに紐づけていけば、マイノリティの人たちにも広がっていくかもしれません。
―「将来」や「未来」について、どれくらいのタイムスパンで考えることが多いですか。
山田:大きな変化という意味では、少なくとも10年以上は見ます。2013年にCollableを立ち上げたときは、インクルーシブデザインはあまり認知されていませんでしたが、現在はそれを専門とする人も少しずつ増えてきました。それはこの10年のあいだで見られるようになったことです。自分のマイルストーン的な意味合いでは、3年という数字を決めていて、3年やって変わらなければ方向転換をしたり、やり方を変えたりしようと決めています。それらを総合して、10年やらなければ変わらないだろうと思っています。
―これからの10年で山田さんが変えたいことは何ですか。
山田:障害のある人たちが社会の中で自分なりの役割を持ち、安心して暮らしていけるようなビジョンを、もう少し具体的に見えるようにすることです。そのために、現在は大学生のキャリアにフォーカスした取り組みを行っています。
大学生は、自分のアイデンティティーが問われる時期です。例えば、何らかの先天性の障害がある学生が、就活を始めるときに、障害があることを含めて自分自身のことをどうやったら相手に伝えることができるのかという問題に直面します。そのときに、障害も含めた自分自身を自らが受け入れなければ就活は難しくなります。
そのために始めたのが「ギャザリング」という取り組みです。多様なキャリアの選択肢を持てること、特に障害のある人が若いときからそのことを知り、生きていけるための仕組みができれば良いと思っています。まずは心理的安全性のようなものが生活の中で担保できると、誰かとアイデアを考えたり、ワークショップに参加したりすることができ、社会との接点ができると思っています。
―社会が大きく変わると様々な影響が出てきますが、それらを取り除くのは困難であり、その変化を受け止められることが重要であると感じます。就活で悩むことと気候変動の対策で影響を受けることは同じことではないですが、根底ではつながっているように思います。
山田:就活は、自分の周囲が変わるという意味で、よりダイレクトな影響があります。気候変動対策に関しても、法律や制度が変わったときに、今までとは異なった仕事のやり方が求められる人が出てくる可能性があります。そのときに、他の選択肢が提供されていたり、企業によって何か新しいサービスが開発され提供されたりすることで、困りにくくなる可能性があります。そうしたことが何もないまま変化だけが起こると、せっかく時間かけて自らの仕事の環境を作ったのに、またゼロから取り組まなければならなくなってしまいます。
―それを未然に防ぐためのケアという発想がこの評価枠組につながっています。一方で困った事態が生じたときに、できるだけ早くその声が生成され、収集されて何らかのアクションにつながるような枠組の両輪が必要だと思います。
―気候変動は社会的弱者が影響を受けると言われていて、障害のある人はその最たる存在としてイメージされます。その場合、障害のある人が自ら気候変動問題の当事者として、強い関心を持つための経路はあるのでしょうか。
山田:例えばEVの価格がとても高くなるという話はイメージしやすいと思います。自分たちが身近に使っているものが、環境にどのようなダイレクトな影響があるのかを丁寧に説明されると、自分事にしやすいと思います。もう一つは、ソーシャルアクション的な側面に関して、現在の20~40代の人たちのあいだでは、以前の社会運動とは異なり、楽しくキャッチーなかたちで取り組もうとする動きが広まりつつあるように思います。
(2021年9月21日、オンラインでインタビュー)
やまだ さゆり
特定非営利活動法人Collable代表
1988年生まれ。大分県出身。重度知的障害を伴う自閉症の兄と弟の間で育つ。大学院では、インクルーシブデザインや環境学習デザインの切り口から、障害のあるなしに関わらないワークショップに関する実践研究を行う。大学院修了後、障害者や高齢者、マイノリティなど、誰もが包摂される学びの環境づくりを実践するべくNPO法人Collableを設立。*所属・役職は当時
自然や文化などの内在的価値の重要性
ソーシャルビジネスコンサルタント
辻井 隆行さん
 ―評価枠組をどのようにご覧になりましたか。
―評価枠組をどのようにご覧になりましたか。
辻井:3E+Sでは抜け落ちていた部分が補われている点が素晴らしいと思いました。私は人間の究極の目的は、(それぞれが考える)幸せになることだと考えていますが、それが右側の3列で補われていると思います。この評価枠組がZ世代などに浸透して、国民的な議論になれば、エネルギー基本計画を策定する際の議論などでも参照され、活用される可能性を感じました。
また、政治を通じた影響の「民主主義・地方自治等への影響」は重要なポイントだと考えています。今後、社会は中央集権型から自立分散型へと移っていくのではないかと思いますが、その移行のプロセス自体が、トップダウンではない自立分散型である必要があると思っているからです。
―具体的には、どのようなことを経済効率性以外の観点で見ていく必要があるでしょうか。
辻井:欧米と日本の自然観には全く異なった意味合いがあります。日本では18世紀頃にオランダ語のナトゥールに「自然」という訳語をあてた経緯があり、そこで、初めて人間が自然から切り離されて、「自然」が客体化されました。
修士論文で、秋田と青森にまたがる青秋林道建設の動きについて研究したことがあります。マタギの子孫の人たちは「私たちが何代にも渡って山と関わってきたからこそ、これまでその環境が守られてきた」と主張する一方、ユネスコは、ここには何人たりとも入ってはいけないという、「MAB(Man and the Biosphere)計画」を提示し、両者の間で衝突が起こりました。そうした自然観を持つ日本人にとって、「自然を壊す」、「自然を直す」と言う考え方自体が馴染みにくのではと思う一方で、近代的な技術の開発を止めることは現実的ではない。だから、例えば、ソーラーの大規模開発が起きたときに、里山と人の関係性も評価軸に入れておけば、例えば、パーマカルチャーや土壌の健康に取り組んでいる人たちなど、より多様な視点も入り、枠組への理解や協力が進むのではないでしょうか。
―人と自然との関係性に関して、都市と地方の人たちのあいだに違いはあるのでしょうか。
辻井:都市と地方でそれほどの違いはないと思います。海外も日本も、近代的な自然観とそれ以前のものが分断されているように感じます。例えば、北米の先住民であるインディアンが、大型の家電を海に捨てるのを見たことがあります。近代文明が入り込む前は、木くずや果物の皮など、捨てるものには海で分解される有機物しかなかったことが影響しているのかも知れません。日本でも熊の貽(い)を高く売るために熊撃ちをしていたマタギの末裔が、自分の犬が死んだときに、金のために動物の命を奪うのは可哀想だからマタギをやめたと口にするのを聞いたことがあります。そういう事例から、近代化以前の自然観というのは、現実的な日常の中では失われつつあるのかな、と感じています。
現在関わっているサステナブルファッションにおいても、「サステナブル」という言葉の使い方に違和感を持っています。サステナブルは、全てのことを自然環境が回復できるスピードの範囲内で取り組むこと、もしくは取った分を返すということだと考えています。カナダの先住民は杉を切って家を建てたり、カヌーを作ったりしてきましたが、30年かかって育つ木は、30年に1本しか切らないような暮らし方を実践してきました。そうした自然との関わり方を考慮せず、テクノロジーだけに頼るようなサステナビリティの議論は危険だと思います。
そのことを踏まえると、脱炭素の技術を導入する上で、「文化・伝統・自然などの内在的価値」に関わる人たちに意見を聞くことは重要だと思います。社会の中で新しいテクノロジーの問題が顕在化してきたときに、そのカウンターとして別の技術に取り組んだとしても、必ず何らかの副作用が出てきます。そのことを常に気に留めておくようなマインドセットが大切だと思います。大きなスパンで考えたときの副作用の歯止めが、3E+Sにはないと思っていました。今回の枠組は、それに対してもある程度ブレーキを掛かる警告の役目を、右側の列が果たしているのではないでしょうか。
―「将来」や「未来」について、どれくらいのタイムスパンで考えることが多いですか。
辻井:私は現在53歳なので、身体的な感覚として想像できるのは50年後ぐらいの未来までです。あとは、自分が死ぬまでと考えれば、30年後の未来だと思います。2100年のことは、正直想像がつかないのですが、1968年からこれまでの間の変化を考えれば、2070~80年にはSFの中でしかなかったような出来事が起きるかもしれないですね。
―日本独自の自然感覚に関して、若い世代と上の世代で違いはあるのでしょうか。
辻井:世代というよりは、DNA的な部分が大きいと思っています。例えば、クーラーの冷たい涼しさよりも、木陰に入った時の柔らかなそよ風の方が気持ち良いという感覚は、全ての人が教えられなくても持っているのではないでしょうか。それは若い人の中にも感じます。例えば、大学生の友人である井上寛人さんは、パーマカルチャー的にビルの屋上に土壌を持ち込んで野菜を作ることで、CO2を吸収しながらウェルビーイングを高めるような取り組みをしています。気候変動へのアクションもZ世代の権利を声高に主張するというよりも、今このときの幸せを実感したいという思いがあるようです。パタゴニアの若いスタッフたちの中にも食品部門を立ち上げたり、農業に取り組んだりする人が増えました。
―人間と自然のあいだの豊かなつながりに向かうものと、それとは反する商品や事業には違いがあると思います。両者をどう区別したらよいのでしょうか。
辻井:私はそれを二つに分けています。一つはサービスや製品そのもの、二つ目は提供している組織や会社です。
サービス・製品は、それを作れば作るほど、自然環境が回復するようなタイプのもの、もしくはそのまま環境に還るものが持続可能で、率直に言えば、そうではないものは持続可能ではないと考えます。だからといって後者のものを使わないわけではありません。
企業の場合、白か黒と言えば、全ての企業が黒になってしまいます。その中で、大事なことは2つあります。1つは一貫性で、外部不経済の内部化に真剣に取り組んでいるかどうか。現状では未達成でも一貫性を持って、それに取組もうとしているかが重要だと感じます。もう1つは時間軸の中でしっかりとコミットメントを公表しているかどうかです。
―サービスや製品を選択する際に生じる葛藤やジレンマは、世の中が成熟していることの裏返しだと思いますが、なかなか難しい問題だと感じています。
辻井:そうですね。今の社会は、持続可能性という意味では非常に不完全です。ほとんどの企業が外部不経済を引き起こしながら事業利益を上げているのは、その一例です。ほとんどの人が「消費者」である現代社会で、一人一人が完全に持続可能性を担保した生活を送ることは難しい。 ですが、その一方で、外部不経済の内部化に真剣に取り組む企業を応援したり、声を発信したりすることは出来ます。消費者の声が大きくなれば、企業は変わらざるを得ないし、それに合わせて規制緩和や税制優遇の仕組みができるかも知れません。私たちは、微力ではありますが、変化の担い手になることはできるのではないかと感じています。
(2021年9月22日、オンラインでインタビュー)
つじい たかゆき
ソーシャルビジネスコンサルタント、元パタゴニア日本支社長
1968年生まれ。東京都出身。大学院時代には、「日本の自然観」をテーマに修士論文を執筆。パートタイムスタッフとしてパタゴニアに入社し、ストア勤務、マーケティング部門、卸売り部門を経て、09年から19年まで支社長。現在は、企業やNPOのビジョン・戦略策定を支援しながら、市民による民主主義や未来のあり方を問い直す活動を続けている。*所属・役職は当時
⇒脱炭素化技術のテクノロジーアセスメント フロントランナーへのインタビュー PART4
- 地域の人が自ら使える道具としての評価枠組の可能性………………………小松理虔さん
- ベンチャーへの投資で進む社会的インパクトの評価…………………………岩田紘宜さん
- 新しい技術を社会に導入する上で包括的な評価枠組が必要 ………………流郷綾乃さん

