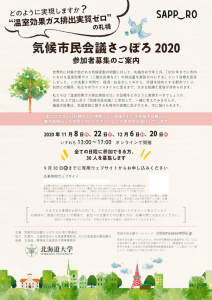プロジェクト
気候市民会議さっぽろ2020
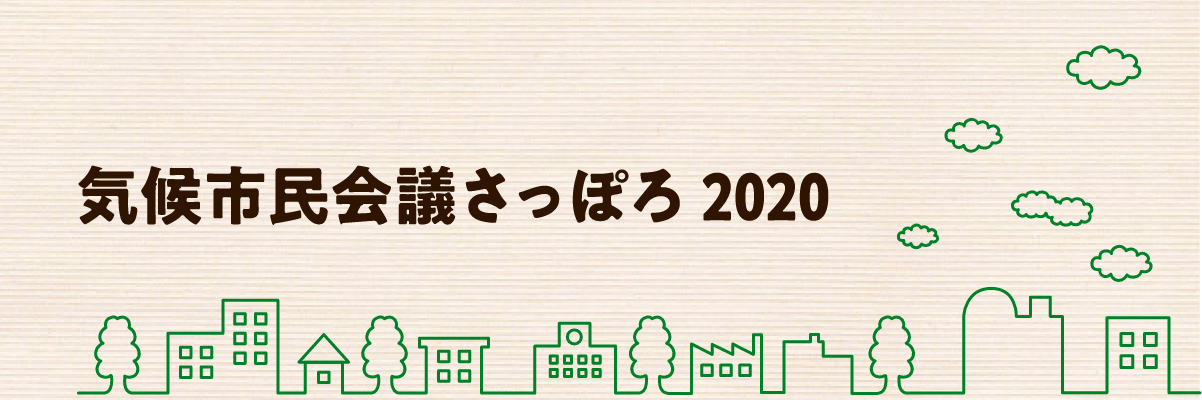
気候市民会議さっぽろ2020とは
温室効果ガス排出実質ゼロの脱炭素社会をどのように実現すべきかについて、くじ引きなどで選ばれた一般の市民が議論し、結果を国や自治体の政策に生かす気候市民会議。2019年頃から欧州など諸外国で広がっているこの会議を、2020年11月から12月にかけて全国で先駆けて開催したのが「気候市民会議さっぽろ2020」です。日本における脱炭素社会の実現に向けた取り組みにいかに応用できるか、気候市民会議の可能性を探る実践的研究(アクションリサーチ)として試行しました。
気候市民会議さっぽろ2020では、16歳以上の札幌市民約172万人の中から無作為抽出で、年代・性別が札幌市全体の構成に近づくよう20人を選出しました。選出された市民は、「札幌は、脱炭素社会への転換をどのように実現すべきか」をテーマとした会議に、オンラインで計4回、16時間にわたり参加しました。参加者は、参考人からの情報提供を聞き、質疑応答とグループに分かれての話し合いを行ったうえで、脱炭素社会のビジョンや実現の時期など計70項目についてオンラインで意見を投票しました。
投票でまとまった会議結果『気候市民会議さっぽろ2020報告書速報版』は、2021年1月19日に公表され、1月25日に札幌市に届けられました。この会議結果は、市内における温室効果ガスの排出を2050年までに実質ゼロとする目標を掲げている札幌市において、気候変動対策行動計画の策定や実行などの取り組みに活用されています。
タイムテーブルと資料、当日の録画
【主催】気候市民会議さっぽろ2020実行委員会
【協力】札幌市、北海道環境財団、RCE北海道道央圏協議会
【後援】北海道、環境省北海道地方環境事業所
結果報告
最終報告書(2021年3月発行)
気候市民会議さっぽろ2020最終報告書(北海道大学HUSCAPのページに移動します)
報告書速報版(2021年1月発行)
気候市民会議さっぽろ2020報告書速報版(北海道大学HUSCAPのページに移動します)
報告シンポジウム(2021年3月20日開催)

気候市民会議さっぽろ2020報告シンポジウムレポートPART1
気候市民会議さっぽろ2020報告シンポジウムレポートPART2
[気候市民会議シンポジウム] 第1部「気候市民会議と札幌市の気候変動対策」録画と資料
[気候市民会議シンポジウム] 第2部「「気候市民会議さっぽろ」結果の読み解き方・生かし方」の録画公開
[気候市民会議シンポジウム] 第3部「日本における気候市民会議の可能性と課題」の録画公開
研究メンバー
江守 正多(東京大学未来ビジョン研究センター教授/国立環境研究所地球システム領域上級主席研究員、気候変動の将来予測とリスク論)
田村 哲樹(名古屋大学大学院法学研究科教授、政治学・政治理論)
松浦 正浩(明治大学大学院ガバナンス研究科教授、合意形成論・交渉学)
池辺 靖(日本科学未来館科学コミュニケーション専門主任、科学コミュニケーション)
工藤 充(公立はこだて未来大学システム情報科学部准教授、科学技術社会論・科学コミュニケーション)
岩崎 茜(国立環境研究所社会対話・協働推進オフィスコミュニケーター、科学コミュニケーション)
八木 絵香(大阪大学COデザインセンター教授、科学技術社会論・災害心理学)
三上 直之(研究代表者・北海道大学高等教育推進機構准教授、環境社会学・科学技術社会論)
***
気候市民会議さっぽろ2020は、科研費基盤研究(B)「公正な脱炭素化に資する気候市民会議のデザイン」(JP20H04387)の一環として実施しました。
2020年4月〜2023年3月(予定)
公正な脱炭素化に資する気候市民会議のデザイン
研究代表者:三上直之
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20H04387/
活動の様子 一覧
小学生向けSDGs教材『SDGsをさがせ!』に、気候市民会議さっぽろ2020が紹介されました
『北海道大学 サステイナビリティレポート2021』で紹介されました
札幌市生涯学習センターの講座「札幌市が目指す脱炭素社会~気候市民会議を活かした取り組み~」でお話ししました
札幌市生涯学習センターの講座で「気候市民会議さっぽろ2020」の取り組みをお話しします
[気候市民会議シンポジウム] 第3部「日本における気候市民会議の可能性と課題」の録画公開
[気候市民会議シンポジウム] 第2部「「気候市民会議さっぽろ」結果の読み解き方・生かし方」の録画公開
[気候市民会議シンポジウム] 第1部「気候市民会議と札幌市の気候変動対策」録画と資料
【3/20シンポジウム:市民の対話でつくる脱炭素社会の将来像】プログラムと資料